2025年5月2日
職場内のハラスメント防止対策のポイント 3
・・・テーマ3 ハラスメント防止対策のポイント・・・
裁判例を見ると、法律上の損害賠償責任を負うようなハラスメントについては、不適切という次元を超えて「違法」との評価を受ける場合に限られています。ただ、会社側として、違法とは言いきれない言動やすぐに懲戒の対象とはならないようなグレーゾーンの言動でも「ハラスメント行為は許さない」というスタンスを従業員に示していくことが、ハラスメントを防止していくためには必要です。
テーマ3では、ハラスメント防止対策のポイントをご説明いたします。
■ポイント1:社内規程・社内ルールの中に、ハラスメント防止の項目を作成する
就業規則や職場における服務規律などを定めた社内規程・社内ルールに、「ハラスメントを行ってはならない」旨の事業主の方針のほか、ハラスメントの定義、具体例、ハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定(※)、被害者に対して会社が行う措置(相談窓口等)などを記載するようにしましょう。きちんと規定することで、具体的にどのような行為がハラスメントに該当するか、ハラスメントが行われた場合、会社がどのような対応をとることになるかなど、従業員に伝えることができます。会社がルールを明確化し、そのルールを従業員に認識してもらうことでハラスメント防止の効果が期待できます。
なお、ハラスメント行為を理由とする懲戒処分を行うには、懲戒解雇事由が就業規則などに定められていることが必要です。“会社を守る”ためにもしっかり規定化しておきましょう。就業規則に記載した場合には、就業規則の変更などの手続きを経るようにしてください。
■ポイント2:詳細なルールについては「ハラスメント防止規程」で規定
注意点としては、就業規則の本則に詳細の規定を盛り込んでしまうと、就業規則のページ数が多くなってしまい、従業員が読まなくなってしまうリスクがあります。お勧めの方法としては「ハラスメント防止規程」を別に作成することとし、その規程でハラスメント防止のための詳細なルールを定めるようにしましょう。
一つの規程の中にパワハラ、セクハラ、マタハラについて定める方法と、個別に「パワハラ防止規程」「セクハラ防止規程」「マタハラ防止規程」といったように類型ごとに規程を作成する方法がありますが、どのように定めるかは社内でよく相談の上、判断するようにしてください。

■ポイント3:従業員に周知・啓発するための研修・講習などを実施
就業規則などにハラスメントに関する項目を作成したら、従業員に周知するようにしましょう。従業員がいつでも見られるように、職場の見やすい場所への掲示・備え付け、電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにします(※就業規則は周知した日から効力を発揮します)。
ハラスメントは上司から部下へ行われることが一般的となっているため、研修・講習を行う場合は、“管理者”向け、“従業員”向けの研修をそれぞれ実施されると効果が得やすくなっています。
【管理職に対する研修】
自分自身がハラスメント加害者になる可能性があること、部下からハラスメント被害の相談を受けた場合に上司としてどのように対応するべきかなど。
【従業員に対する研修】
自分がハラスメント被害者になった場合、同僚がハラスメント被害者となった場合にどうするべきか、ハラスメントと指導教育の違い、逆パワハラなど。
また、感情をコントロールする手法や、コミュニケーションスキルアップ、マネジメントや指導についての研修等の実施などもお勧めです。一度だけでなく、定期的に、繰り返し実施するとより効果が上がります。自社での教育が難しい場合には、社会保険労務士、コンサルタントなどの専門家に講師を依頼することも検討してみてください。
■ポイント4:相談や解決の場を設置
従業員ができるだけ初期の段階で、気軽に安心して相談できる相談窓口を設置しましょう。パワハラだけでなく、セクハラ、マタハラなどあらゆるハラスメントの相談を一元的に応じることのできる体制を整えます。従業員が相談しやすくするために、秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないこと、相談窓口でどのような対応をするかも就業規則などで明確にしておくことが大切です。
相談窓口には、人事労務担当部門や産業医、労働組合などの“内部相談窓口” 、弁護士や社会保険労務士事務所などの“外部相談窓口”が考えられます。ハラスメントの相談窓口として適切な人材を社内で確保するのが難しい場合は、外部相談窓口の設置も検討されるとよいでしょう。
以上、ハラスメント防止対策のポイントをご説明しました。ハラスメントに対する取り組みは一過性のものに終わってしまうと、ハラスメント対策の重要性が忘れられ、「ハラスメントを許さない」という会社風土が根付かないままとなってしまいます。また、自分では意識せずに、ハラスメント行為を行う従業員も見られるようになってしまいます。そうさせないためにも、繰り返し教育や周知を行っていく必要があるでしょう。
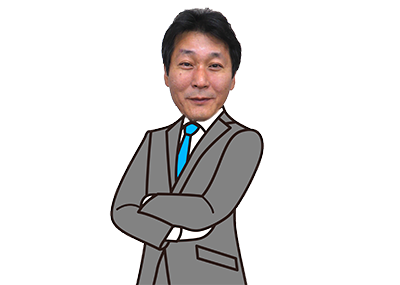
編集者:井上晴司
最近の投稿
- スポットワーク活用における労務管理のポイント
- 年末年始休業のお知らせ
- 年末調整前に確認!
- 求人が受理されない!? 職安法施行令改正で問われる“育児・介護法令遵守”
- 企業実務に影響!年金制度改正法の重要ポイント
よく読まれている記事
カテゴリー
- Money (2)
- お知らせ (68)
- その他 (2)
- チャイニーズウイルス (1)
- ニュース (3)
- ハラスメント (1)
- 健康保険・厚生年金保険 (5)
- 働き方改革推進関連法 (6)
- 副業・兼業 (1)
- 労働安全衛生法 (2)
- 労基法 (5)
- 労災保険 (5)
- 同一労働同一賃金 (8)
- 外国人雇用 (1)
- 大迷惑 (1)
- 年金 (4)
- 懲戒処分 (1)
- 採用情報 (1)
- 法改正 (3)
- 災難 (2)
- 社労用語じてん (2)
- 福利厚生 (2)
- 賃金 (2)
アーカイブ
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (3)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (5)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年3月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (4)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (6)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (1)
