2025年4月30日
職場内のハラスメント防止対策のポイント 2
昨今、ハラスメントに対して厳しい目が向けられています。ハラスメントが起き、ひとたび悪評が立つと、企業価値やコーポレートイメージの著しい低下を引き起こし、また、職場内の離職率・訴訟リスクを高め、生産性も悪化するなど、大きな経営リスクを伴います。
この時流を受け、2025年3月11日に、政府はカスハラ防止を全企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定しました。今回は、テーマ1をふまえて、テーマ2では、職場で起きやすいハラスメントの種類についてご説明いたします。
・・・テーマ2 職場で起きやすいハラスメントの種類・・・
■法的に整備されている「職場で起きやすいハラスメントの種類」とは
ハラスメントとは、人の尊厳を傷つけ、精神的・肉体的な苦痛を与える“嫌がらせ”や“いじめ”、不利益を与えたりする行為全体を指します。一口にハラスメントと言っても、パワハラ、セクハラのほか様々な種類があります。以下は、法的に整備されている“職場で起きやすいハラスメント”の種類をまとめたものとなります。
| パワーハラスメント
(パワハラ) |
優越的な関係に基づいて、業務上明らかに必要かつ相当な範囲を超えた言動などで、身体的・精神的な苦痛を与えたり、労働者の就業環境を害したりすること |
| セクシュアルハラスメント
(セクハラ) |
相手の意に反する性的な言動によって、相手に不利益を与えたり、就業環境が害されたりすること。就業環境が不快となることで労働者の能力の発揮に悪影響を及ぼすといった弊害もある |
| SOGIハラスメント
(ソジハラ) |
性的指向(※1)や性自認(※2)を理由に差別や嫌がらせ、社会的な不利益を与えること。セクハラの一つ |
| マタニティハラスメント
(マタハラ) |
妊娠、出産、育休などを理由とする解雇・降格・配置転換、雇い止めなどの不利益な取り扱いのこと |
| パタニティハラスメント
(パタハラ) |
男性が育児休業制度などを利用することに対して行われる嫌がらせや、降格・自主退職の強要等 |
| ケアハラスメント
(ケアハラ) |
家族のために介護休業制度などを利用することへの嫌がらせや、人事評価を下げるなどの不利益を与える行為のこと |
(※1)人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
(※2)性別に関する自己意識
上記のハラスメントは、いわゆる3大ハラスメント“パワハラ”、“セクハラ”、“マタハラ”に分類されるもので、「労働施策総合推進法」や「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」において、事業主に防止措置を講じることが義務づけられています。

次に、上記のほか、職場で起きやすい“〇〇ハラスメント”について見てみましょう。
■職場で起きやすい“〇〇ハラスメント
| コロナハラスメント |
新型コロナウィルス感染症に感染し、職場復帰した社員Aに対し、他の社員が感染したのは「Aが感染源である」と一方的に断定し、感染経路を問いただしたり長時間叱責したりする等 |
| ジェンダーハラスメント
|
“男らしさ”“女らしさ”にふさわしい言動を強要したり、そぐわないことを非難する言動のこと。セクハラの一つ
|
| エイジハラスメント
(エイハラ) |
世代や年齢の違いを理由とした差別的な言動や嫌がらせ。世代ごとの志向の決めつけなども。 |
| リモートハラスメント
(リモハラ) |
在宅勤務によってオンライン会議等での連絡が増えることで起きるパワハラ、セクハラを指す |
| テクノロジー・ハラスメント(テクハラ)
|
PC、スマートフォン、タブレット端末等機器の扱いが不得手な人物へのいじめや嫌がらせのこと
|
| ソーシャルメディア・ハラスメント(ソーハラ)
|
職場での優位性を利用して、友人登録などを強要する等SNSを通じた嫌がらせ、不利益を与える行為
|
| セカンドハラスメント(セカハラ)
|
ハラスメント被害者が、その被害について相談した相手から責められたり、嫌がらせを受けたりすること
|
| ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)
|
自分が不快に感じる言動を何でもハラスメントと決めつけて過剰に騒ぎ立てること。逆ハラスメントに該当
|
| 逆ハラスメント | 部下から上司、後輩から先輩に対するいじめ・嫌がらせ。下の地位・立場にいる者からのハラスメントであることから、そう呼ばれる |
職場で起きやすい“〇〇ハラスメント”には様々なものがあることをご理解いただけたことと思います。これらのハラスメントは元を辿れば、3大ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)のいずれかに分類されます。
■そのトラブルがハラスメントに該当するかどうかよく精査する
労働者間のトラブルが起きたときの注意点としては、従業員から「Bさんの■■行為は、〇〇ハラスメントである」と相談を受けた際に、それが法律上のハラスメントに該当するようなものであるか、よく精査・調査することです。ハラスメントに該当する可能性が高いか低いかで、その後の対応が異なってきます。自社で判断がつきそうにもない場合は、ハラスメントに詳しい専門家へ相談のうえ、対応することをおすすめします。
次回は、「テーマ3 ハラスメント防止対策のポイント」です。
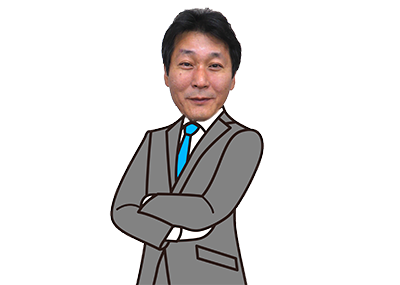
編集者:井上晴司
最近の投稿
- 年末調整前に確認!
- 求人が受理されない!? 職安法施行令改正で問われる“育児・介護法令遵守”
- 企業実務に影響!年金制度改正法の重要ポイント
- 夏季休業のお知らせ
- 中小企業向けカスタマーハラスメント防止対策のポイント テーマ3
よく読まれている記事
カテゴリー
- Money (2)
- お知らせ (66)
- その他 (2)
- チャイニーズウイルス (1)
- ニュース (3)
- ハラスメント (1)
- 健康保険・厚生年金保険 (5)
- 働き方改革推進関連法 (6)
- 副業・兼業 (1)
- 労働安全衛生法 (2)
- 労基法 (5)
- 労災保険 (5)
- 同一労働同一賃金 (8)
- 外国人雇用 (1)
- 大迷惑 (1)
- 年金 (4)
- 懲戒処分 (1)
- 採用情報 (1)
- 法改正 (3)
- 災難 (2)
- 社労用語じてん (2)
- 福利厚生 (2)
- 賃金 (2)
アーカイブ
- 2025年10月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (3)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (5)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年3月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (4)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (6)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (1)
